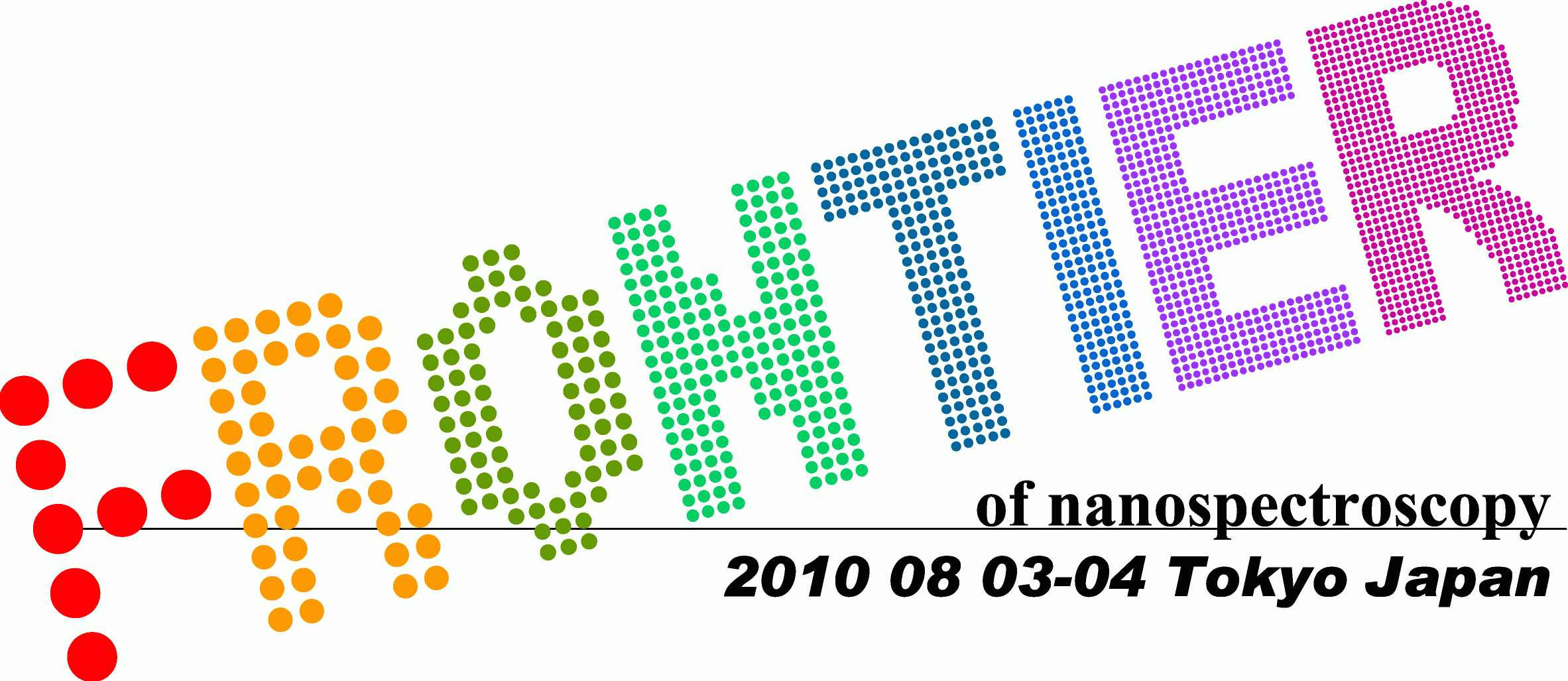
日本放射光学会第二回若手研究会 「顕微分光のフロンティア」
2010年8月3〜4日
東京大学 本郷キャンパス 工学部1号館 15号講義室
こちらの研究会は、終了いたしました。
各方面よりご参加・ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
アンケート結果を掲載しました。
研究会の写真アルバムがご覧になれます。
| 放射光によるナノスケールの顕微分光は、物質の機能解明のための強力なツールであり、将来の低炭素社会に向けたグリーンナノテクノロジーにおいて、中心的な役割を担うものと予想される。本研究会では、シーズである顕微分光技術の進展と、ニーズである材料科学のホットな話題を相互に発表し、これらの交わりを通じて、近未来の顕微分光における次の一手を模索し、将来の発展に繋げることを目的とする。 技術開発の観点からは、PEEM、STXM、3次元NanoESCA等の顕微分光技術を中心に、先行開催されたナノ集光技術研究会や次世代光源であるXFELからの意見を伺う。また利用の観点からは、主要なターゲットであるナノ磁性の話題を中心に、生命科学から惑星科学まで幅広い分野の話題提供を予定しており、全体を俯瞰した視点から顕微分光技術のフロンティアを目指す。そして今回は若手の特色ある研究をコンパクトに濃縮し、"Espresso"的に話題提供を行うセッションを企画した。より現場に近い観点から、若手を発信源とした新しいサイエンスに繋がることも期待している。 |
参加費:無料
モバイル版ウェブサイトは こちらから▼  または http://www.jssrr.jp/wakate10/mobile/mobile_top.html 会場の位置やプログラム等が 携帯電話からご確認できます。 |
プログラム(敬称略)
8月3日(火) 10:00〜18:00
開会の挨拶 放射光学会長 尾嶋正治(東大) 研究会趣旨説明 小嗣真人(JASRI) (10:10〜12:00)
PEEM を用いた顕微分光研究の現状と新展開 小嗣真人(JASRI) 軟X線走査型顕微分光法の現状と将来展望 荒木暢(豊田中研) 走査型X線顕微鏡による磁気観察 鈴木基寛(JASRI) 三次元走査型光電子顕微鏡 堀場弘司(東大) (13:00〜14:30)
硬X線集光技術の現状と顕微分光への期待 矢代航(東大) コヒーレントイメージングの現状と展望 西野吉則(北大) 「1nmスケール化学分析」へのアプローチ 齋藤彰(阪大)
遷移金属酸化物抵抗変化メモリーにおける局所相変化機構 藤原宏平(理研) 中空球殻形状磁性体の特性 照井通文(NICT) カーボン系デバイスのための観察及び分析装置 大南祐介(日立ハイテク) 休憩(15:55〜16:05) (18:00〜)
|
8月4日(水) 9:00〜17:50
休憩(10:30〜10:40)
休憩(14:40〜14:50)
|
代表: 小嗣真人(JASRI) (谷内敏之(東大)、大河内拓雄(JASRI)、小野寛太(KEK))
主催:日本放射光学会
後援:JST-CREST 超高輝度放射光機能界面解析・制御ステーション

